![]()
2-166
夞憐偺幒惗帥丂徍榓俆俀擭搤偺晽宨
丂係俉擭傕慜偵側傞徍榓俆俀擭搤偺旘捁楬峴偱弰偭偨壀帥偲媖帥偺偆偪媖帥傊偼儈僉僆孨偲曕偄偨俆擭慜偺旘捁楬峴偱傕攓娤偟偰偄偰偟偐偟摿偵報徾偵巆傞傛偆側偙偲偑側偵傕側偔儂乕儉儁乕僕偵婰帠偼彂偐側偐偭偨偑係俉擭慜偺媖帥傕摨偠偱偙傟偲偄偭偨報徾偑側偐偭偨偺偵懳偟壀帥偼報徾怺偐偭偨丅壀帥偼奐慶偑媊暎乮偓偊傫乯偲偄偆崅憁偱偁偺峴婎乮偓傚偆偒乯傗椙曎乮傠偆傋傫乯偼偦偺掜巕偩偲偄偆偐傜偢偄傇傫屆偄偍帥偩丅堦曽偱旘捁傜偟偝傪姶偠偝偣側偄偍帥偩偑偦傟偼懞奜傟偺崅偄媢偺忋偵偁偭偰柧擔崄懞偱偼捒偟偄尰栶偺娤壒楈応偩偐傜偩傠偆丅
丂暓憸傪娤傞椃偲偄偆偙偲偱尵偊偽係俉擭慜偺旘捁楬峴偱偼壀帥偺偛杮懜偑杮柦偱偳傫側暓條偐偲嫽枴捗乆偩偭偨丅偦偺杮懜偼擛堄椫娤壒曥嶧嵖憸偱旘捁暓偱偼傕偪傠傫側偔揤暯傕屻婜偺嶌偱偦傟偑傏偔傜偺抦傞俇杮榬偱曅旼棫偰偨擛堄椫娤壒偺巔偱偼側偄晛捠偵恖娫偺巔傪偟偰偄偰偟偐傕忎榋乮偠傚偆傠偔乯偡側傢偪係.俇儊乕僩儖偲偄偆嫄戝側慪憸偩偭偨偐傜傏偔偵偼偦傟偩偗偱尒傞慜偐傜堎條偵巚偊偰偄偨偑偦傟偑栵彍偗偺娤壒條偩偲偄偆偺偩偐傜偙偺栚偱尒傞偲偳偙偐晄婥枴偵偝偊姶偠偰偦偺奃怓偺敡偵僝僢偲偟偨丅壀帥偺暓憸偵偼傎偐偵崙曮偱栘怱姡幗偺徰憸挙崗偺寙嶌偲偟偰柤崅偄奐慶媊暎偺嵖憸偑偁傝娤偰偄傞偼偢側偺偵妎偊偰偄側偄偺偼傛傎偳擛堄椫娤壒憸偺報徾偑嫮楏偩偭偨偺偩傠偆丅
丂偲偙傠偱杮摪撪恮偼壀帥偺儂乕儉儁乕僕偵傛傞偲侾寧偐傜俁寧偼堦斒偺攓娤偑偱偒側偄偲側偭偰偄傞丅栵彍偗朄梫偺偨傔偩偲偄偆丅傏偔偑峴偭偨偺偼俀寧偺枛偛傠偩偭偨偑妋偐偵杮摪偱杮懜傪娤偨婰壇偑偁傞丅偦偺偙傠偼搤偱傕攓娤偱偒偨偺偐偁傞偄偼姴晹岓曗惗妛峑偵偄偨偙傠偵傕弔愭偵峴偭偰偄傞偐傜偦偺偲偒偺婰壇偲偛偭偪傖偵側偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅偄偢傟偵偟偰傕俆擭慜偺旘捁楬峴偱偼儈僉僆孨偵偙偺嫄戝擛堄椫娤壒憸傪尒偣偰偤傂姶憐傪暦偒偨偄偲偄偆巚偄傕偁偭偨偑壀帥偲媖帥偺椉曽偼帪娫揑偵傕懱椡揑偵傕柍棟偱旘捁帥偺偁偲偳偭偪偵偡傞偐傪柪偭偰寢嬊屻栠傝偣偢偵旘捁墂偵峴偗傞媖帥偵偟偰偄偨丅壀帥偵偟偰偍偗偽傛偐偭偨偲偄偆婥偑崱峏側偑傜偟側偄偱傕側偄丅
 |
| 壀帥偺恗墹栧丂挀幵偟偰偄傞徍榓俆侽擭戙偺幵偑夰偐偟偄 |
丂偙偺婰帠偼傒偭偮慜偺乽柧擔崄懞偺柉廻乿偺懕偒偱偁傞丅乽柧擔崄懞偺柉廻乿偱偼柉廻偱弌憳偭偨恖偺偙偲傪彂偄偨偑偙偺偲偒偺旘捁幒惗傊偺侾攽俀擔偺椃偼偦傕偦傕屆檵弰傝偩偭偨偺偩偐傜偦偺暥柆偐傜尵偭偰傕柉廻偩偗彂偄偰廔傢傜偣傞偲偄偆朄偼側偔偦偺偲偒弰偭偨偍帥傗暓憸偺婰帠偑屻偵懕偔偺偑嬝偲偄偆傕偺偩丅偦傟偱偙傟傪彂偄偰偄傞偺偩偑偡偖偵彂偐偢擔壽偺僂僅乕僉儞僌傗夞憐偺ORIGIN僔儕乕僘偑娫偵擖偭偰偟傑偭偨偺偼側偤偐偲尵偊偽僀儊乕僕偑晜偐傇偲偦傟傪懄嵗偵彂偔偲偄偆偺偑偙偆偄偭偨婥傑傑側儂乕儉儁乕僕偺僗僞僀儖側傫偩偲庍柧偟偰傒偰傕彮偟傕傢偐偭偰傕傜偊側偄偩傠偟偦傟偑傏偔偺婥暘偩偲尵偊偽傑偡傑偡側傫偺偙偲偐傢偗偑傢偐傜側偄偲巚偆偑丄娫偑嬻偄偨偲偄偆偺偼偮傑傝偼偦偆偄偆偙偲偩偭偨丅傏偔偺傛偆側暥昅壠偲偄偆傢偗偱偼側偄慺恖偑彂偔偙傫側婥妝側暥復偱傕偄偞彂偔偲側傞偲峫偊偑傑偲傑傜側偄偱偼彂偗側偄傕偺偱傑偨慺恖偩偐傜傑偲傔傞偲偄偆偙偲偑悳傞壓庤偱偦偆偙偆偟偰偄傞偆偪偵懠偺婰帠偑摢偵晜偐傃偁傞偄偼慜乆偐傜偳偆彂偙偆偐偲擸傫偱掆懾偟偰偄偨婰帠偑撍慠慜恑偟偰偟傑偆偲朰傟側偄偆偪偵偲偦偭偪偑愭偵側偭偨丅傏偔偺儂乕儉儁乕僕偑杮棃懕偗偰彂偔傋偒婰帠偑嶶傜偽偭偰偄傞強埲偱偁傞丅傏偔偺彂偒曽偲偄偆偺偼愭偵嵟屻偵抲偔暥復偺僀儊乕僕偑摢偺拞偵晜偐傫偱偦偺捈屻偵偦偺懳偲側傞彂偒弌偟偺暥復偺僀儊乕僕偑晜偐傃偦偺彂偒弌偟偲嵟屻傪宷偖杮暥傪偔傫偢偹傫偢偟偰彂偔偲偄偆僗僞僀儖偩偐傜偦偆側傞偺偱偁偭偰丄偦偺嵟屻偲彂偒弌偟偺僀儊乕僕偑摢偵晜偐偽側偄偲偳偆偵傕側傜側偄偺偩偟媡偵偦偺僀儊乕僕偝偊晜偐傋偽師乆偵彂偄偰偟傑偆丅偙傫側偙偲傪彂偄偰偄傞偺偼梫偡傞偵乽柧擔崄懞偺柉廻乿偲崌傢偣偰撉傫偱偔偩偝偄偲偄偆偙偲偱丄偦傟側傜娙寜偵堦尵偦偆尵偊偽嵪傓偙偲側偺偩偑丄偱傕偦傟偱偼壠揹偺庢愢傒偨偄偱偦傫側偺偮傑傜側偄偱偼側偄偐丅乮偔傫偢偹傫偢偼嬥戲偺曽尵偱偲偰傕嬯楯偡傞偙偲丅乯
丂柧擔崄懞偱柉廻偵堦攽偟偰梻擔偼幒惗傊峴偭偨丅幒惗岥戝栰偱戄偟帺揮幵傪庁傝偰傑偢偡偖偦偙偺戝栰帥傊婑偭偨偲婰壇偟偰偄傞丅崱偼攓娤椏傪庢傞傛偆偩偑偁偺偙傠偼攓娤帺桼偩偭偨偺偩傠偆丅偙偙偱偺偍栚摉偰偼戝栰帥偐傜悢昐儊乕僩儖棧傟偨偲偙傠偵偁傞杹奟暓偱幒惗愳乮塅懮愳乯塃娸偺戝偒側娾偵嫄戝側栱栌擛棃棫憸偑棳楉側慄崗偱昤偐傟偰偄偨丅彮偟偆偮傓偒壛尭偵帇慄傪棊偲偟偨偳偙偐廌偄傪娷傫偩旤偟偄栱栌暓偱姍憅弶婜偺傕偺偩偲偄偆丅摉旜偺愇暓弰傝偺夞偱彂偄偨乽儈儘僋偺捯乿偺杹奟暓傪渇渋偲偝偣傞偑偙偪傜偑埑搢揑偵戝偒偄丅嵍壓偵偁傞墌偺側偐偵偼戝彫偨偔偝傫偺瀽帤傕崗傑傟偰偄傞丅懜彑欀涠梾偩偲偄偆偑偦傟偑偳偆偄偆傕偺偐偼抦傜側偄丅壓偺幨恀偼愳偵増偭偨摴楬偐傜懳娸偺杹奟暓傪嶣偭偨傕偺偱慄崗偼偐側傝傢偐傝偯傜偄偑搤側偺偱庤慜偺晼傜偟偄栘偼梩傪棊偲偟塭傕側偔憪傕屚傟偰偄偰杹奟暓偺慡懱憸偑傛偔傢偐傞丅壓偺曽偵幨偭偰偄傞偺偼幒惗愳偺棳傟偱妷悈婜側偺偐悈偼彮側偄丅偙偺栱栌暓傪娤傜傟偨偩偗偱傕偙偙傑偱棃偨抣懪偪偑偁傞傛偆偵巚偊偨丅
 |
| 戝栰栱栌杹奟暓丂崅偝偼侾係儊乕僩儖傕偁傞 |
丂幒惗愳偺慂偮嫭扟傪嵍偵塃偵尒側偑傜嬋偑傝偔偹偭偨摴傪幒惗帥傊岦偗偰帺揮幵傪憱傜偣傞丅傛偔惏傟偨擔偱廮偐偵拲偖搤偺擔嵎偟偼抔偐偱傕晽傪愗偭偰憱傟偽杍偵庴偗傞晽偼椻偨偔摴楬傢偒偺擔堿偵側偭偰偄傞幬柺偱燌傒弌偟偨抧壓悈偑搥偭偰偮傜傜偵側偭偰偄偨丅偙偺婫愡偵幒惗帥傊峴偔恖偼彮側偄丅搑拞帺揮幵偼傕偪傠傫幵偵捛偄敳偐傟傞偙偲傕偡傟偪偑偆偙偲傕側偐偭偨丅
丂壓偺幨恀偼幒惗岥戝栰偱壠暲偺墱拞墰偵撍偒弌偰偄傞壆崻偑戝栰帥丅杹奟暓偼偦偺嵍偵尒偊傞業弌偟偨悅捈偺娾敡偵崗傑傟偰偄傞丅幒惗帥偼嶳暲傒偺梱偐岦偙偆偱幒惗愳増偄偺摴傪朌偆傛偆偵偟偰俈僉儘峴偭偨偲偙傠偵偁傞丅
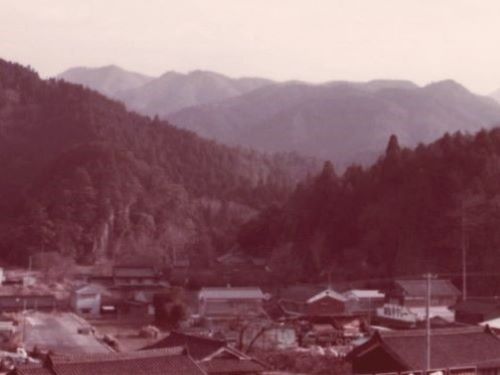 |
 |
| 幒惗宬扟丂幒惗帥傊偺摴偼幒惗愳偵壦偐傞偄偔偮傕偺嫶傪搉傞嬋偑傝偔偹偭偨摴 |
丂幒惗帥偼恀尵枾嫵偺帥偱懢屰嫶傪搉偭偰偡偖偺昞栧偲奪嶁壓偺恗墹栧偺愇拰偵乽彈恖崅栰乿偲偁傝愄偼彈偺恖偼崅栰嶳偵偼搊傟偢偙偙側傜擖傟偨偲偄偆偺偩偑丄崱偱傕晄曋側偙傫側嶳偺拞偵偙傫側棫攈側偍帥傪寶偰偨偺偼尗鹠乮偗傫偗偄乯偲偄偆尦嫽帥偺朧偝傫偩偭偨丅挬掛偺柦傪庴偗偰偺偙偲偱峜懢巕帪戙偺姾晲揤峜偑昦婥偵側偭偨偲偒棿恄偵墔楈戅嶶偺婩摌傪偟偰岟偑偁偭偨偙偲偑墢偩偲偄偆偐傜榖偼暋嶨偱傢偐傝偵偔偄丅幒惗偼崱傕愄傕愭偢棿恄怣嬄偺棦偱偁傞丅
丂幒惗帥偺杮摪偼擛堄椫娤壒嵖憸傪杮懜偲偡傞燇捀摪偩偑攓娤偺拞怱偼嬥摪偱娤偨偄偺偼偦偺撪恮偩丅廫堦柺娤壒曥嶧偼偠傔俆懱偺棫憸偺慜偵侾侽懱偺廫擇恄彨偑寗娫側偔暲傇丅偙偺廫擇恄彨偼傏偔偵偼憿宍昞尰偑嬅傝夁偓偵尒偊偰偁傑傝岲偒偱偼側偄偑侾俀懱懙偭偰偄側偄偺偼偍偦傜偔僗儁乕僗偺娭學偱慡晹暲傋傜傟側偄偐傜偱偳傟偐俀懱偑忢偵撧椙攷傊婑戸偵弌偰偄偨丅侾俀懱慡晹娤偨偗傟偽椉曽傊摨帪婜偵峴偔昁梫偑嵟嬤傑偱偁偭偨丅嵟嬤傑偱偲偄偆偺偼嬤偛傠嬥摪偺彅暓偺堦晹偼怴愝偺曮暔娰偵堏偝傟廫堦柺娤壒曥嶧棫憸傗抧憼曥嶧棫憸側偳偵崿偠偭偰廫擇恄彨傕敿暘偑偦偙偵偁傝巆傝偺敿暘偼栻巘擛棃偺慜偱墶堦楍偵梋桾偱暲傫偱偄傞偦偆偩丅
丂偲偙傠偱懡偔偺暓憸偑擹枾偵傂偟傔偔愄偺嬥摪撪恮偼憇娤偲尵偊偽憇娤偩偭偨偑傗偼傝彅暓偑擹枾偵暲傇搶帥島摪偲偼偪偑偭偰偨偩暲傋棫偰偨偩偗偱偳偙偐晄帺慠偵傕尒偊偰偁偪偙偪偺壏愹廻偱偍搚嶻偵攦偭偰棃偨偙偗偟傪媗傔崬傫偩拑偺娫偺拑抃恲偺忋偵嵹偣偨僈儔僗偺捖楍働乕僗傒偨偄偱傏偔偼岲偒偱偼側偐偭偨丅偱傕偁偺偙偗偟傒偨偄偵暓憸偺暲傫偱偄偨條巕偑崱偼傕偆尒傜傟側偄偺偼偪傚偭偲庘偟偄傛偆側婥傕偡傞丅恖偺巚偄偲偼彑庤側傕偺偱偁傞丅
 |
| 幒惗帥偺嬥摪丂奜娤偼摨偠偱傕撪恮偺條巕偼崱偱偼偢偄傇傫曄傢偭偰偄傞傜偟偄 |
丂嬥摪偺慜偺峀応偵栱栌摪偲偄偆偍摪偑偁偭偰側偐偵偼抙憸晽偺栱栌曥嶧棫憸偑杮懜偲偟偰埨抲偝傟偰偄傞偑傏偔偑峴偭偨偲偒偺摪撪偵偼側傫偱偦偙偵偁傞偺偐傢偐傜側偄偲偄偆庍夀擛棃嵖憸偑杮懜偺嵍椬偵偁偭偨丅庍夀暓偱偼側偔栻巘暓偩傠偆偲尵傢傟偰偄傞偙偺擛棃憸傕崱偼曮暔娰偵揥帵偟偰偄傞偲偄偆丅
丂栱栌摪偺懳柺偵幒惗帥偲偼柍墢偺懞偺捔庣幮偺攓揳偑偁偭偰偦偺墶偵偪傚偭偲戝偒偔棫攈側孯涠棙柧墹偺愇暓偑偁傞丅偩傟傕婥偵傕棷傔側偄偙偺愇暓娤偨偝偵幒惗帥傊棃偨偲尵偊偽傑偨傑偨戝孶嵕側偙偲傪尵偆恖偩偲巚偆偩傠偆偑栚揑偺係俋亾偼偦偆偩偭偨丅偦傟偼偲傕偐偔孯涠棙柧墹傕愇暓偵偡傞偲偐傢偄偄傕傫偱嵍塃偺尐偐傜弌傞俉杮偺榬偑奍偺懌傒偨偄偵峀偑傞丅孯涠棙柧墹偺榬偺悢偼嫻偺慜偱岎嵎偝偣傞僿價偑姫偒偮偄偨榬傕娷傔偰俉杮偑寛傑傝偩偑偙偺愇暓偼侾侽杮偁傞傛偆偵尒偊傞丅
 |
| 捔庣幮偺墶偵偁傞孯涠棙柧墹偺愇暓 |
丂孯涠棙柧墹偺愇暓偼岦偐偭偰嵍墶偺孍傒偵乽斚擸懄曥採丂惗巰懄煾炏乿偲擔杮暓嫵偺恖娫娤偑崗傑傟偰偄傞丅曥採傕煾炏傕屽傝偵摓傞偙偲偱恖娫偼側傫偺偨傔偵惗偒傞偺偐偲偄偆塱墦偺栤偄偵孯涠棙柧墹偑偙偨偊偰偔傟傞偺偩傠偆丅丂俀侽俀俆擭俆寧俋擔丂屨杮怢堦乮儊僉儔丒僔儞僄儌儞乯
幨恀丂屨杮怢堦
丂儂乕儉丂栚師丂慜偺儁乕僕丂師偺儁乕僕
丂偛堄尒偛姶憐側偳傪偍暦偐偣偔偩偝偄丅儊乕儖偼偙偪傜傊偍婑偣偔偩偝偄丅偍懸偪偟偰偄傑偡丅